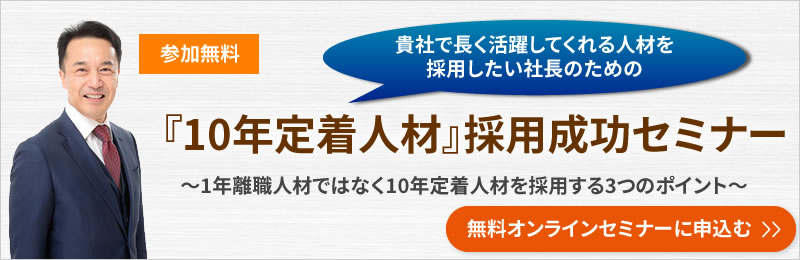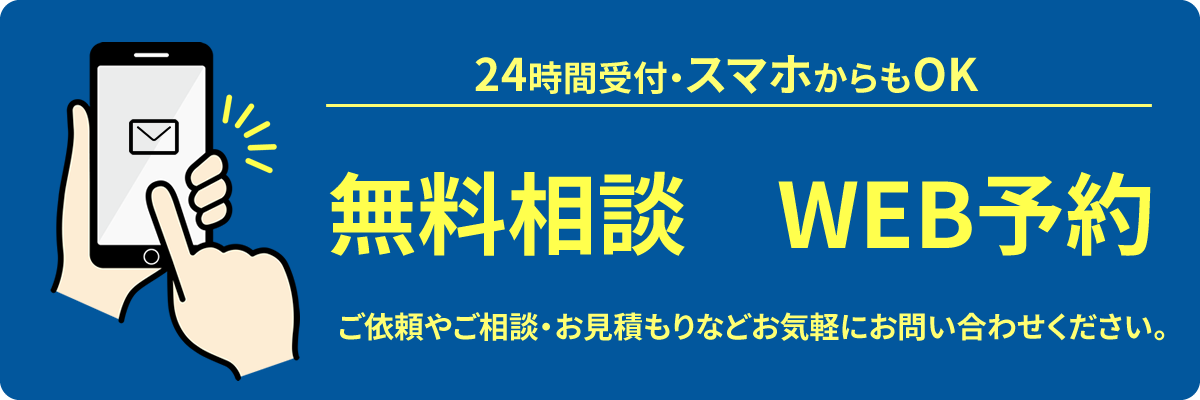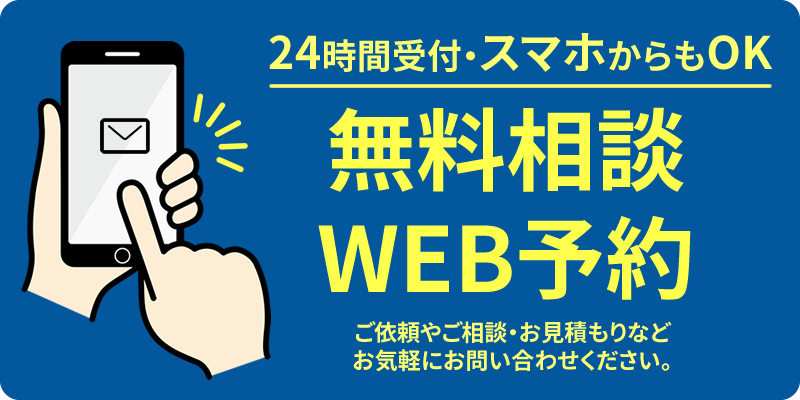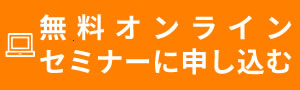若手が選ぶ企業の条件とは?Z世代の“心の声”を読み解く
近年、「若手がすぐ辞める」「内定辞退が増えている」といった声を多くの企業が挙げています。その背景には、Z世代と呼ばれる若年層の価値観の変化があります。
1990年代後半から2000年代に生まれたZ世代は、デジタルネイティブとして育ち、SNSや動画コンテンツに囲まれて生活しています。彼らは“情報を選ぶ力”に優れ、自分の価値観に合わない情報や組織には積極的に距離を置く傾向があります。
本コラムでは、Z世代の“心の声”を読み解きながら、彼らが「この会社で働きたい」と思う企業の条件を、採用・定着の観点から紐解いていきます。
Z世代の就職活動におけるこだわり
かつての就職活動は「企業が学生を選ぶ」スタイルが主流でした。しかしZ世代は「自分に合った会社を選ぶ」スタンスを強く持っています。
インターンシップやSNS、口コミサイトなどから事前に情報を収集し、企業の文化や職場の雰囲気をよく観察したうえで応募を判断します。給与や福利厚生といった条件以上に、「その企業でどんな人と、どんな感情を持って働けるか」を重視するのです。
また、Z世代は“直感”を重視する傾向もあります。形式的な採用情報よりも、動画で見た社員の雰囲気や、SNS上のやりとりから「なんとなく合いそう」と感じた企業に魅力を感じます。採用ブランディングのあり方も大きく変化してきているのです。
Z世代が企業に求める5つの条件
Z世代の心の奥にある「選ぶ基準」は、必ずしもこれまでの常識と一致しません。以下は、彼らが企業選びにおいて重視しているとされる5つの視点です。
1. 自分らしく働けるか
Z世代は“個性”や“多様性”を重視します。画一的な価値観や古い慣習に縛られた企業よりも、自分の考えやスタイルを尊重してくれる企業を好みます。服装や髪型の自由度、意見を言いやすい雰囲気があるかどうかも、判断材料になります。
2. 職場の人間関係が良好か
「誰と働くか」を非常に大切にするのがZ世代の特徴です。上下関係よりも“フラットなつながり”を求め、共感できる仲間や安心できる上司がいるかどうかがカギとなります。採用面接時の社員対応やインターンシップの現場体験を通じて、その雰囲気を敏感に読み取っています。
3. 社会的意義が感じられるか
Z世代は「社会にとって意味のあることに関わりたい」という意識が強く、企業の理念やSDGsへの取り組みなどをチェックしています。給料だけでなく、“誇りを持てる仕事”かどうかが選択の要素です。仕事の目的が曖昧な企業よりも、「この仕事が誰かの役に立っている」と実感できる環境に魅力を感じます。
4. 柔軟な働き方が可能か
コロナ禍を経験して育ったZ世代は、リモートワークやフレックス制度などの“自由度”を求めています。仕事とプライベートを分けるというより、両立するライフスタイルを望む傾向があります。
5. 成長とフィードバックがあるか
常に学びたい、成長したいという意欲があるZ世代は、“育ててくれる環境”を重視します。定期的なフィードバックやコーチングのある企業は魅力的に映ります。また、キャリアの道筋が明確に示されていることも、安心感と意欲を引き出す要因になります。
企業側が意識すべき3つのポイント
Z世代に“選ばれる企業”になるためには、以下のような姿勢が求められます。
1. 発信力を高める:自社の文化や働き方、価値観を積極的に発信する。SNSや動画など、Z世代に響く媒体での情報提供が有効です。採用ページのデザインやトーン、社員のリアルな声の発信が共感を得る鍵となります。
2. エンゲージメント重視の職場づくり:「心理的安全性」「感謝の文化」「共感型マネジメント」など、感情的つながりを大切にした職場を目指すことが、定着率向上に直結します。Z世代は、評価制度以上に“気持ちの通じ合い”を大切にしています。
3. “感情”に配慮した採用設計:スキルや経歴以上に、価値観や感情の相性を意識した選考・面接のあり方を取り入れることが重要です。たとえば、グループワークや対話重視の面談を通じて、お互いの“共鳴”を確かめる採用スタイルが効果的です。
まとめ:Z世代に選ばれる企業とは、“感情に敏感な会社”
Z世代の若者たちは、情報も感情も敏感にキャッチします。 企業が一方的に“選ぶ”時代は終わり、いかに共感を得るか、いかに信頼を築くかが問われる時代に突入しています。
採用活動は、単なる人材確保ではなく、企業文化の発信でもあります。Z世代の“心の声”を丁寧に聞き、共に未来を創るパートナーとして向き合う姿勢こそが、これからの採用・定着戦略の要となるでしょう。
「何を与えるか」よりも「どう感じさせるか」・・・
それが、Z世代に選ばれる企業の条件です。