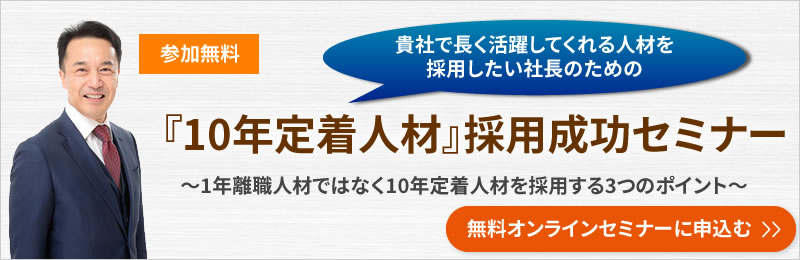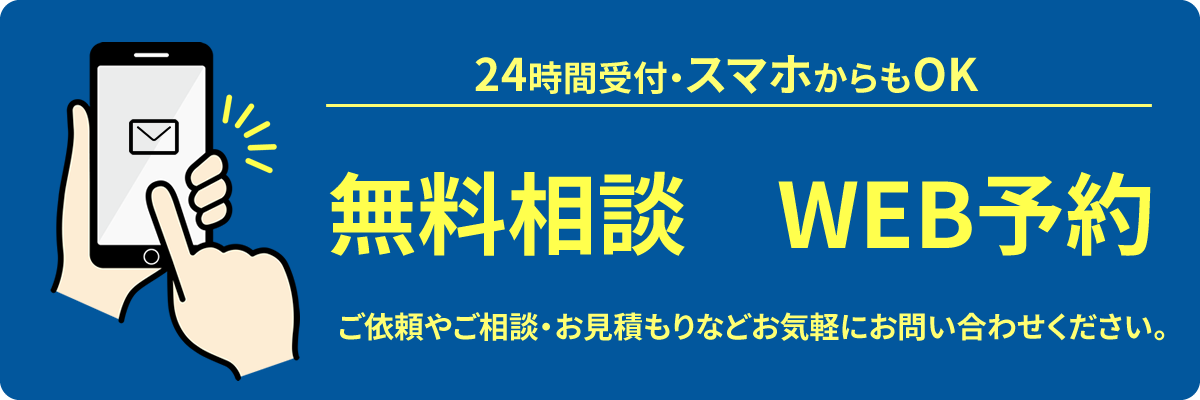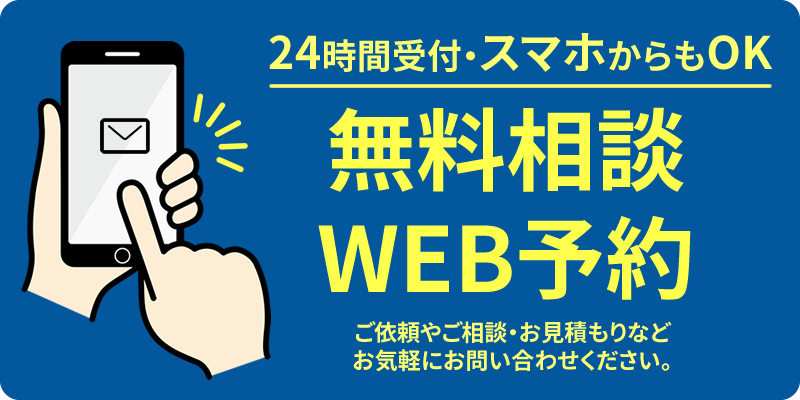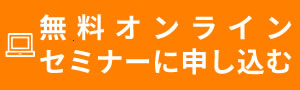採用ミスマッチの原因は“共感のズレ”?成功する企業が実践する5つのポイント
「採用時に当社の理念や大事にしている価値観をしっかり説明したのに、すぐに辞めてしまった」
そんな“採用ミスマッチ”の声は、多くの企業で後を絶ちません。私自身も採用セミナーをしていると各企業様のお悩みとしてこのケースが多く挙がります。
スキルや経歴は申し分ないのに、なぜ人材の“ズレ”が起きてしまうのでしょうか。
その背後にある見えない要因こそが、“共感設計”のミスです。
共感設計とは、求職者が企業や上司の価値観・感情・考え方に共感できるかどうかを、採用の最初から設計しておくこと。
この視点が欠けると、いくら求人票を整えても、面接を丁寧にしても、結果的にミスマッチが発生します。
今回は、採用における共感設計のズレが引き起こす5つの代表的な失敗について解説します。
1. 面接で「良いこと」しか伝えず、現場とのギャップが生まれる
多くの企業が犯しがちなミスは、「ウチは働きやすい会社です」「やりがいのある仕事です」と、ポジティブな情報だけを強調してしまうことです。
実際の職場には緊張感があったり、スピード感が求められたりと、独自の文化があるはずです。
この “温度感”をあらかじめ伝えておく設計ができていないと、入社後に「話が違った」となり、早期離職につながります。
共感設計とは、現場の空気や上司の価値観まで含めて、“その人に合っているか”を判断できる状態をつくることです。
2. 求職者の「価値観」ではなく「能力」ばかり見てしまう
履歴書や面接で評価されるのは、どうしてもスキルや経験になりがちです。
しかし、入社後に活躍できるかどうかは、価値観が組織と合うかどうかにかかっています。
たとえば、「丁寧さを重視する組織」に対して「スピード重視の人」を採用してしまえば、摩擦が生じてしまいます。
これは能力の問題ではなく、感覚の違い=“共感のズレ”によるミスマッチです。
3. 面接官が「会社の顔」になっていない
共感設計の要は、面接の場にあります。
求職者は、面接での上司・担当者の態度や話し方から、「この会社で働くイメージが持てるか」を判断しています。
たとえば、面接で話しをした上司が冷たい印象だった、リアクションが少なかった、などが理由で「この会社は合わないかも」と判断されることも。
“この人と働けそうか”を伝える場としての共感設計がなされていないと、せっかくの優秀な候補者を逃してしまうことにもなりかねません。
4. 求人票やHPが“内向き発信”になっている
求人票や企業HPも、共感設計において非常に重要です。
「自社の強み」だけを並べるのではなく、求職者が「ここで働くことにどんな意味があるか」を感じられる構成が求められます。
感情に訴えかけるコピーや、社員の本音が見えるストーリーこそが、 “共感トリガー”となります。
5. 採用後の“オンボーディング設計”がない
仮に共感を得て採用できたとしても、入社後に「共感が持続しない」環境であれば、意味がありません。
• 初日のウェルカムメッセージがない
• オリエンテーションが形式的
• 上司が忙しくて話しかけられない
こうした初期の体験が、入社したばかりの社員の気持ちを冷めさせてしまいます。
共感設計とは、“入社前から入社後”にかけて一貫して感情設計されている状態のこと。
ここまで丁寧に整えることで、採用ミスマッチは大きく減少します。
まとめ:「共感の設計」が、採用成功の新スタンダード
スキルの合致よりも、感情の一致が採用のカギとなる時代です。
「なぜこの会社で働きたいのか」
「どんな人と働きたいのか」
「この環境で自分が幸せになれるか」
その答えを求職者が描けるように設計されていない限り、採用は“博打”になってしまいます。
これからの採用は、条件交渉だけではなく“共感設計”も大切です。
人の心を理解し、組織との共鳴を丁寧に設計することが、
採用しても辞めない持続可能な組織づくりの第一歩となります。