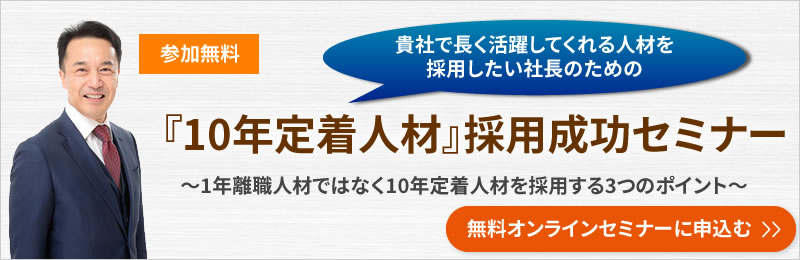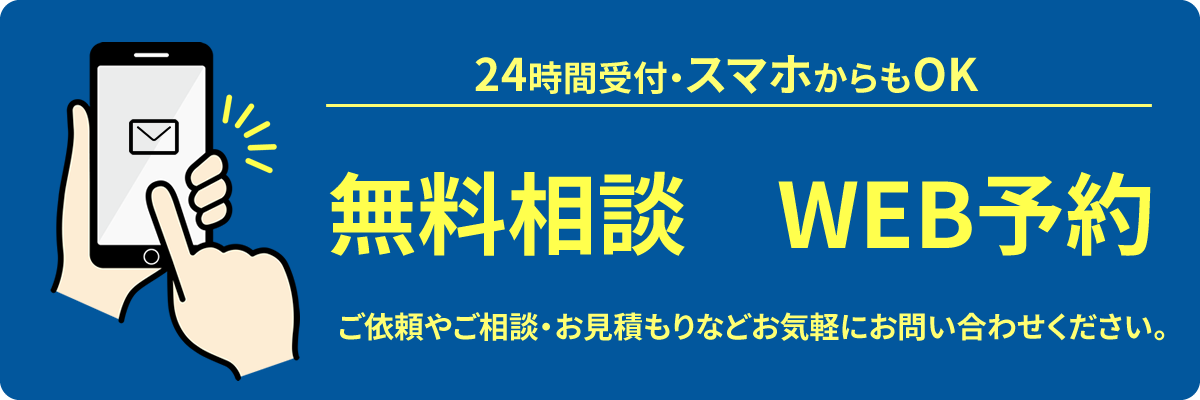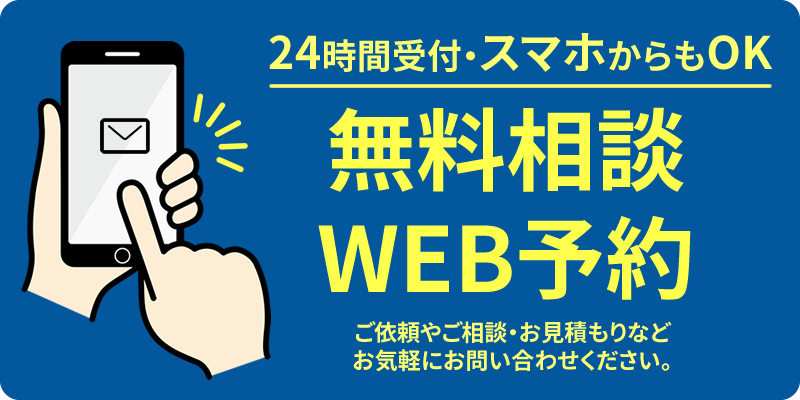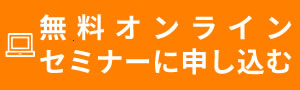採用ブランディングで社員の定着率を高める3つの方法
採用活動は「人を集めるためのもの」と捉えられがちですが、その取り組み方次第で、社員の“定着率”に大きく影響することをご存じでしょうか? 本コラムでは、心理学の視点を交えながら、「採用ブランディング」が入社後の社員の定着にどうつながるのか、その理由と具体的な方法を解説します。採用で苦戦している企業、定着率に悩む経営者・人事担当者の皆様に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
「採用活動」がその後の「定着率」に大きな影響を与える
企業経営において、「採用」と「定着」は別々の課題として語られることが多くあります。しかし、実はこの2つは深くつながっています。その橋渡しをするのが、「採用ブランディング」です。多くの経営者・人事担当者は、採用活動の際に「どうやって良い人材を集めるか」に注力しますが、実はその採用活動そのものが、入社後の“定着”にも大きな影響を与えていることをご存じでしょうか?
採用ブランディングとは何か?
採用ブランディングとは、簡単に言えば「求職者に対して、自社の魅力を戦略的に伝え、入社意欲を高める活動」です。給与や待遇といった“条件面”ではなく、「この会社で働く意味」「ここで働くことで得られる価値」を発信し、求職者の“感情”に働きかけることが特徴です。
近年、特にZ世代やミレニアル世代の採用市場においては、給与や福利厚生以上に「自分らしく働けるか」「共感できるビジョンがあるか」「成長できる環境があるか」という、心理的・感情的なポイントが重視される傾向にあります。
採用ブランディングと定着率の“心理的”つながり
では、なぜ採用ブランディングが定着率に影響を与えるのでしょうか?
その背景には、心理学的な要因が大きく関係しています。
1. 「自己決定感」とエンゲージメント
心理学の「自己決定理論」では、人は自ら選んだものに対して強い責任感や愛着を持つとされています。採用ブランディングによって、自社の理念や職場環境を丁寧に発信し、それに共感した人材が「ここで働きたい」と自発的に応募した場合、入社後のエンゲージメントは自然と高まります。
一方で、十分な情報提供がないまま入社した場合、「思っていた会社と違った」「こんなはずじゃなかった」という期待ギャップが生まれやすく、早期離職につながります。
2. 認知的不協和理論
もうひとつの理論が、認知的不協和理論です。
これは、「自分の行動や選択と矛盾する状況に直面すると、人はその矛盾を解消しようとする」という心理メカニズムです。
採用ブランディングでしっかりと会社の理念や価値観を伝え、それに共感した上で入社した社員は、「自分で選んでこの会社に入った」という意識が強くなります。そのため、入社後に多少の不満や壁にぶつかっても、「自分で選んだ会社なのだから、簡単に辞められない」という心理が働き、自ら会社にとどまる理由を探すようになります。
逆に、採用時に表面的な条件だけで応募・入社した場合、この心理的効果は働きづらく、「思っていたのと違う」と感じた瞬間に離職を選びやすくなります。
ブランディングがないとどうなるか?
採用ブランディングが弱い企業では、採用の時点で「給与」「勤務地」「待遇」など条件面のみで応募者を集めがちです。しかし、これらは他社に簡単に上書きされる要素であり、少しでも条件の良い企業が現れると、社員は転職を考えるきっかけになります。
また、「働く意味」や「会社の価値観」を共有されずに入社した社員は、自分の仕事に対する誇りや目的意識を持ちにくく、ちょっとした不満や人間関係のトラブルで離職を選択しやすくなります。
採用ブランディングを定着率向上に活かす3つのポイント
① 「ありのままの会社」を伝える
ブランディングというと、「良いところだけを発信する」ものと思われがちですが、実際はリアルな情報発信こそが定着率向上に繋がります。入社前に「仕事の厳しさ」や「成長の過程で乗り越えるべき課題」も伝え、入社後のギャップを減らしましょう。
② 求める人物像を明確にする
誰にでも響くメッセージではなく、「こういう価値観の人と働きたい」というメッセージを明確に打ち出すことが重要です。これにより、ミスマッチによる早期離職を防ぐことができます。
③ 社員の声を活用する
「実際に働いている社員のリアルな声」は、最も強力な採用ブランディングコンテンツになります。働く人の本音を発信し、「この会社でどんな成長ができたか」「どんな仲間がいるのか」を求職者に届けましょう。
まとめ
採用活動は「入口」だけの取り組みではありません。採用の時点でどれだけ自社の魅力や価値観を伝えられるかが、入社後のエンゲージメントや定着率に直結しています。
これからの時代、「人が辞めない会社」をつくるためには、採用ブランディングを単なる採用活動ではなく、社員の“定着”と“育成”までを見据えた戦略として捉えることが不可欠です。
「採用したら終わり」ではなく、「採用から定着・活躍まで」を見据えた採用ブランディングに、ぜひ取り組んでみてください。