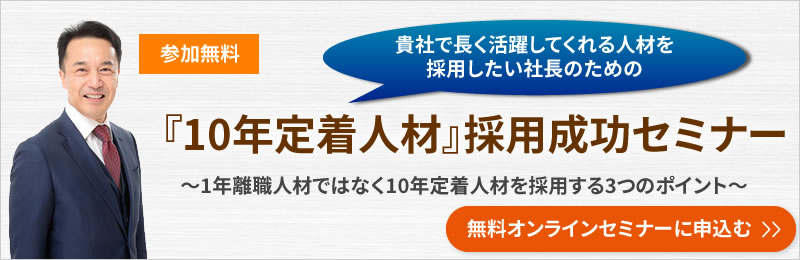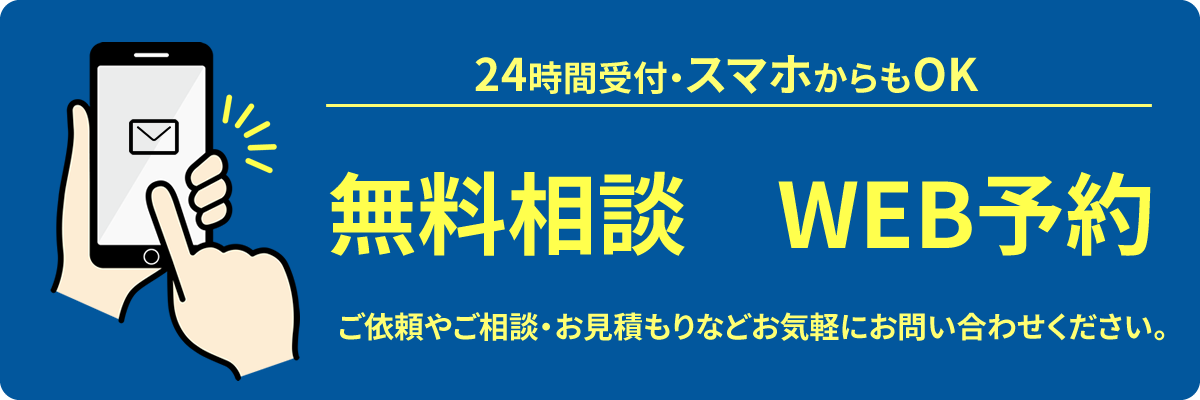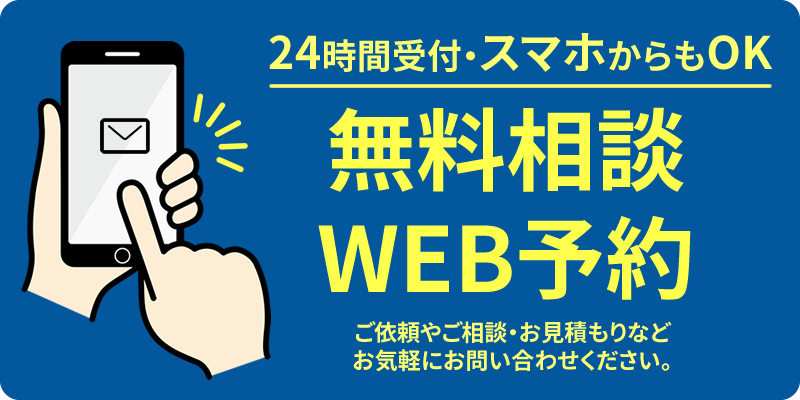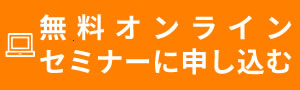新入社員が3ヶ月で辞める理由:職場に足りない“受け入れ体制”とは?
「せっかく採用した新入社員が、3ヶ月もたたずに辞めてしまった…」
そんな経験を持つ企業は、決して少なくありません。
労働市場の変化に伴い、若手人材の定着は年々難易度を増しています。
厚生労働省のデータによれば、新卒の3年以内離職率は30%前後を維持しており、深刻な経営課題です。
この早期離職を防ぐカギとして、近年注目されているのが「オンボーディング」です。
◆ オンボーディングは“情報提供”ではなく“関係構築”である
オンボーディングとは、新たに組織に加わった人材がスムーズに適応し、早期に活躍できるようになるまでの支援プロセスのことです。
しかし、現場では「初日にオリエンテーションを行う」「マニュアルを渡す」「OJTで育成する」といった形だけの導入が多く、本来の目的である“安心と信頼の形成”にまで踏み込めていないケースが非常に多いのが現状です。
オンボーディングの本質とは、「この職場にいていい」と感じられる感情的安全基地を構築することにあります。
◆ なぜ3ヶ月で辞めるのか?──感情の“未処理”が離職を生む
人は新しい環境に入るとき、表面上は意欲的でも、内心では「うまくやれるか」「受け入れてもらえるか」「期待に応えられるか」と不安でいっぱいです。
この心理的不安に対して、周囲が配慮しないまま「業務理解」や「即戦力化」だけを求めてしまうと、本人は感情を処理する間もなく“心が疲れて”しまいます。
心理学者であるフェスティンガーの社会的比較理論によれば、人は自分の状態を他者との比較で評価する傾向があります。つまり、「他の新人はできているのに」「自分だけが取り残されているのでは」と感じると、その不安は自己否定感や疎外感に変わっていきます。
また、「質問しにくい」「相談しづらい」「叱られるのが怖い」といった空気感は、心理的安全性が損なわれている状態であり、これが長引くと人は「ここにいたくない」と感じ始めるのです。
◆ オンボーディングに必要なのは“感情の居場所”
では、早期離職を防ぐオンボーディングとは、具体的に何をすれば良いのでしょうか?
答えは、情報ではなく“感情”に寄り添った設計をすることです。
つまり、「どう教えるか」よりも「どう迎えるか」「どうつながるか」が大切なのです。
以下は、感情に配慮したオンボーディングの実例です。
• 「歓迎されている」と感じられるような初日のチームメッセージを演出する
• 入社から1ヶ月間は、業務成果よりも“頑張っている姿勢”をしっかりフィードバックする
• 直属の上司だけでなく、気軽に話せる“感情の避難場所”となる先輩社員やメンターを用意する
こうした仕組みは、どれも簡単なことのようでいて、感情への理解なしには設計できません。
◆ 組織が果たすべき“心理的インフラ”の構築
オンボーディングのゴールは、業務スキルの早期習得ではなく、「この職場に安心して所属できる」という感情の確立です。
心理学者であるエリクソンが提唱した「基本的信頼感」の考え方によれば、人は安全な環境の中でのみ、自らを肯定し、外の世界と積極的に関わることができます。
企業は、新入社員にとっての“心理的インフラ”=安心・つながり・承認を丁寧に設計する必要があるのです。
これがなければ、いくら制度や待遇が整っていても、職場は「冷たい場所」になってしまいます。
◆ まとめ:「感情設計」こそ、離職を防ぐ本質
人は、論理や制度だけで動く存在ではありません。
特に職場という“人間関係の集合体”では、感情の質こそが、定着と離職の明暗を分ける決定的要因となります。新入社員が3ヶ月で辞めてしまう職場には、たいてい「感情の置き場」がありません。
一人ひとりの不安や孤独に気づき、声をかけ、つながりを感じてもらうことで、ようやく人は「ここで頑張ろう」と感じられるのです。
オンボーディングとは、 “制度の導入”だけではなく、“心の受け入れ”も整えることです。
感情を大切にする迎え入れの設計こそが、早期離職ゼロの組織をつくる第一歩なのです。