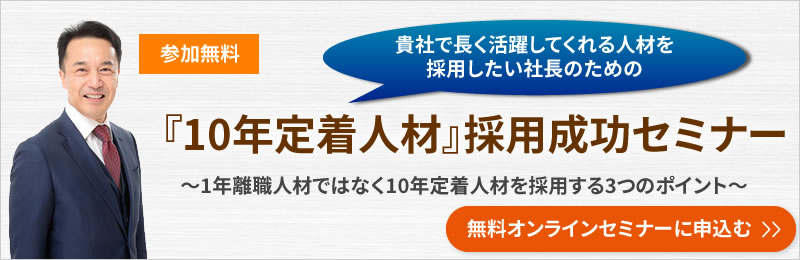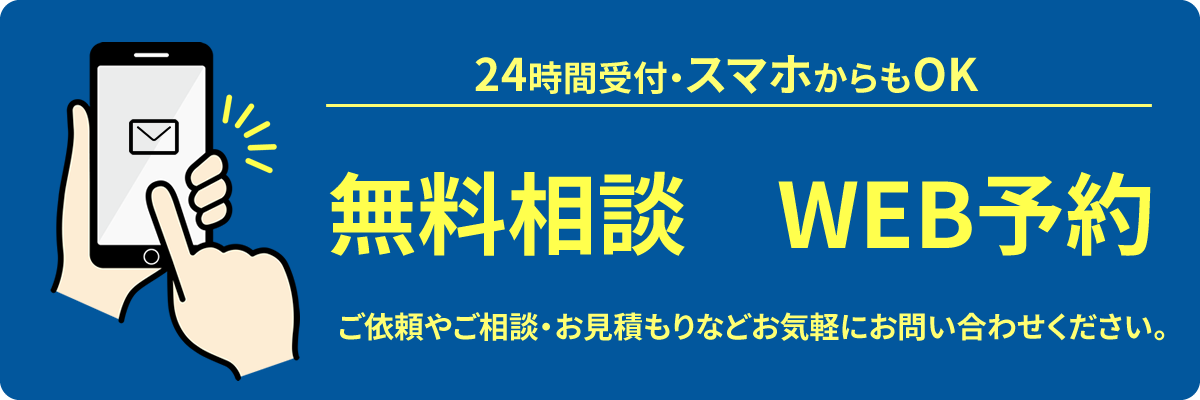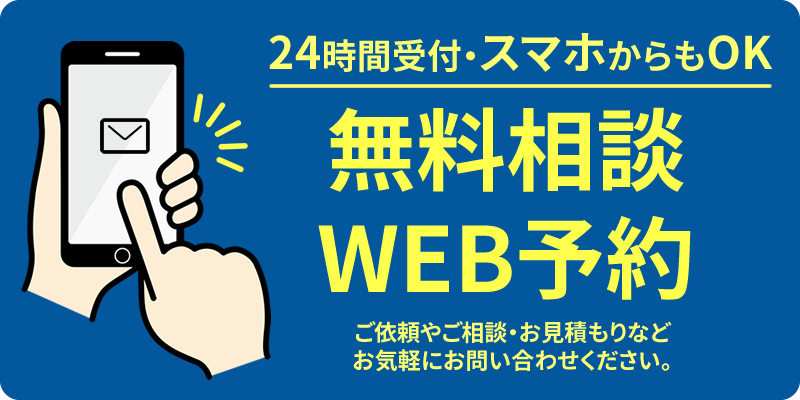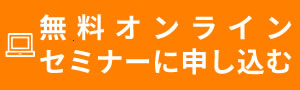「上司のひとこと」が部下の離職を招く? 感情を動かすマネジメントの力とは
「また若手が辞めてしまった」「特に不満はなかったはずなのに」
こうした現象は、今や多くの職場で珍しいことではありません。
制度を整え、給与も悪くない。それでも定着しない。
その理由は、待遇面だけではなく、“感情”が深く関わっていることが心理学的にもわかっています。
そして、その感情に日々影響を与えているのが、上司のひとことなのです。
■ 人は感情で動く。“居心地の良さ”が職場を選ばせる
「人の意思決定は、理屈よりも感情に大きく影響される」これは、心理学や行動経済学の基本的な前提です。
どれだけロジカルに「今の会社に残ったほうが得だ」と思えても、職場で感じる“不安”“違和感”“孤独感”が強ければ、人はそこに留まれません。
特に若手社員やZ世代は、「人間関係」「共感」「安心感」を職場に求める傾向が強いと言われています。
つまり、「この職場にいて居心地が良いかどうか」は、彼らにとって非常に重要な判断基準なのです。
そしてその“居心地の良さ”を決定づけるのが、上司の部下にかける言葉や日々のコミュニケーションなのです。
■ 上司のひとことが、自己評価を変える
心理学には「ラベリング理論」という考え方があります。
これは、「人は他者からどう評価されたかによって、自分自身をそう見るようになる」というものです。
たとえば、部下がミスをしたときに上司が、
• 「やっぱり君はこういうの苦手だよね」
• 「なんでいつもそうなの?」
と言えば、部下は「自分はダメなんだ」と自信を失ってしまいます。
逆に、
• 「今回はうまくいかなかったけど、前より工夫できてたよ」
• 「次に活かせば大丈夫。一緒に考えよう」
と伝えるだけで、部下は「自分は認められている」「前に進んでいいんだ」と感じるのです。
この違いが、離職するか、定着するかの分かれ道になります。
■ 離職を防ぐ「心理的安全性」のつくり方
Googleが行った調査「プロジェクト・アリストテレス」では、高業績チームの共通点として「心理的安全性」の高さが挙げられました。
心理的安全性とは、「この職場では、自分の意見を安心して伝えられる」「ミスしても受け止めてもらえる」と感じられる状態のこと。
これは制度や仕組みだけでは生まれません。上司の日々の言葉や態度が、その空気をつくるのです。
たとえば、忙しさから無意識に無視したり、質問をはねつけてしまったりすると、部下は「何を言っても聞いてもらえない」と感じてしまいます。
逆に、少し立ち止まって「どうした?」「大丈夫?」と声をかけるだけで、相手の感情は驚くほど変わるのです。
■ 感情を支える“ひとこと”とは?
では、部下が「この職場で働き続けたい」と感じるには、どのような声かけが効果的なのでしょうか?
心理学の知見をふまえ、以下にいくつかの例をご紹介します。
● 「ありがとう」で承認欲求を満たす
マズローの欲求5段階説によると、人は「認められたい」という承認欲求を持っています。
「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉は、その欲求を満たし、職場への愛着を育てます。
● 結果より“努力”を認める
バンデューラの「自己効力感理論」では、自分の行動が結果につながるという感覚が、挑戦意欲を高めるとされています。
たとえ完璧でなくても、「工夫してたね」「成長してるね」と伝えることで、自己効力感が育ちます。
● ミスの後に“安心感”を与える
人は失敗したときほど不安になります。そんなときに「この経験は無駄にならないよ」といったひとことがあると、安心感が生まれます。
この小さな声かけが、離職を防ぐ大きな力になるのです。
■ まとめ:言葉の積み重ねが、職場を育てる
人は、日々のやりとりの中で「大切にされているか」「信頼されているか」を判断しています。
だからこそ、上司のひとことが与える影響は想像以上に大きいのです。
離職防止のカギは、制度や給与だけではありません。
部下の感情に寄り添うマネジメントが、これからの組織には求められています。
あなたのひとことが、部下の未来と職場の文化を変えます。
そう思って、今日も部下にひと声かけてみませんか?