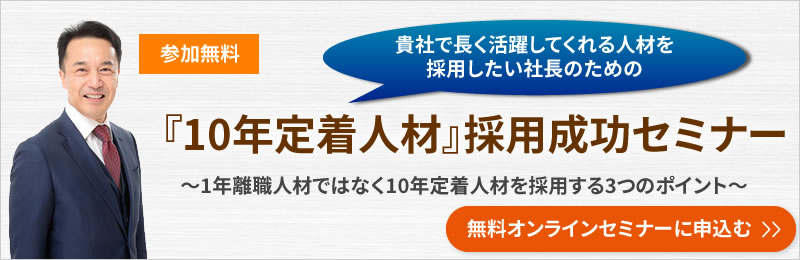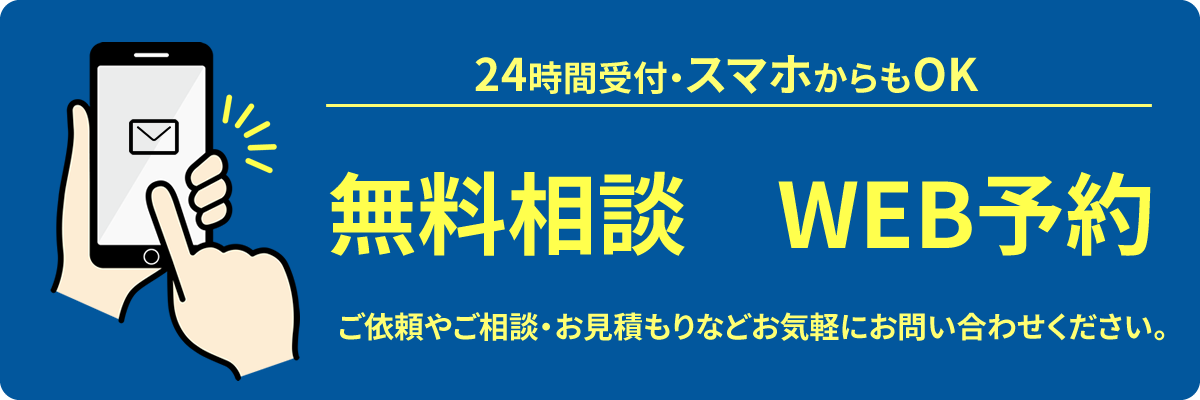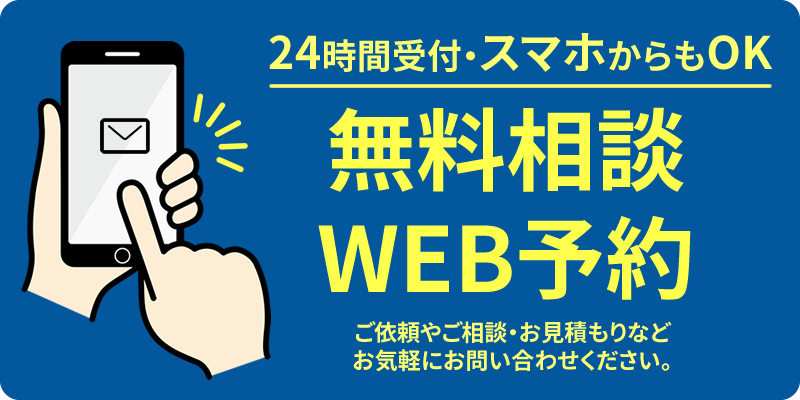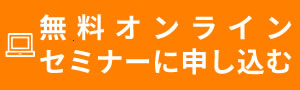内発的動機づけを活かした人材育成 ~人が「自ら育つ」組織づくりのヒント~
「どうすれば人が育ち、長く会社に貢献してくれるか?」
この問いは、多くの経営者・人事担当者・マネージャーが抱える共通の課題です。従来は、知識を与え、正しい手順を教え、評価と指導で成果を出させる「管理型」の育成スタイルが主流でした。しかし、変化の激しい今の時代には、それだけでは通用しなくなっています。大切なのは、「人が自ら育とうとする力=内発的動機づけ」を引き出すことです。
■ 内発的動機づけとは何か?
心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンによって提唱された「自己決定理論」では、動機づけには大きく分けて2つあるとされています。
• 外発的動機づけ:報酬、評価、罰則など、外部からの刺激によって行動すること
• 内発的動機づけ:好奇心、成長欲求、価値観との一致など、内面から湧き上がる動機によって行動すること
もちろん、給与や評価といった外発的要素も重要ですが、それだけでは持続的な成長は生まれません。むしろ、「自分がやりたい」「もっとできるようになりたい」「誰かの役に立ちたい」と感じて動く人は、モチベーションが長続きし、創造性も高まることが分かっています。
■ 内発的動機づけを高める3つの鍵
自己決定理論では、人の内発的動機づけを高めるためには、以下の3つの心理的欲求が満たされていることが重要だとされています。
1. 自律性(Autonomy)
「やらされている」のではなく、「自分で選んでいる」という感覚があること。
選択肢を与えたり、自ら目標を立てさせたりすることで、社員は主体性を発揮しやすくなります。たとえば、「どの研修を受けるかを選べる」「プロジェクトの進め方を自分たちで決められる」など、小さな選択の積み重ねが、自律性を育みます。
2. 有能感(Competence)
「自分にはできる」という手応えや達成感を得られていること。
いくら頑張っても結果が見えなければ、やる気は続きません。段階的な目標設定と、こまめなフィードバックによって「できた!」を積み重ねていくことで、有能感が強化され、より高い挑戦への意欲も湧いてきます。
3. 関係性(Relatedness)
「誰かとつながっている」「自分はここに必要とされている」と感じられること。
職場の人間関係が希薄だったり、孤立していたりすると、モチベーションは低下します。信頼できる上司や同僚との関係性は、心理的安全性を高め、安心して成長に向かえる土台となります。
■ 育成の目的は「教えること」ではなく「引き出すこと」
従来の育成は、「何を教えるか」が中心でした。しかし、内発的動機づけをベースにした育成は、「どう引き出すか」に視点が移ります。人は誰でも、自ら成長したいという欲求を内に持っています。それを引き出すためには、以下のような工夫が効果的です。
• 目標設定を一緒に行い、自分ごとにする
• 行動だけでなく、思考や感情にも関心を向ける
• 承認やフィードバックは、“プロセス”に焦点を当てて行う
• 自由に学べる環境や時間を確保する
• 心理的安全性を確保し、挑戦が歓迎される文化をつくる
育成とは、「正解を与えること」ではなく、「問いを立てられる人」を育てることです。そしてその鍵は、本人の中にある意欲や興味を、どう引き出し、育んでいけるかにかかっています。
■ 内発的動機づけが定着に与える影響
「辞めない人材をどう育てるか?」と聞かれたとき、福利厚生や待遇改善を考える企業は多いですが、実はそれ以上に大切なのが「内面からの納得」です。人は、「この会社で自分は成長できている」「この仕事に意味がある」と感じている限り、簡単には離職しません。
逆に、「成長実感がない」「自分で選べない」「誰からも認められていない」と感じたとき、人は迷わず環境を変えようとします。だからこそ、内発的動機づけを軸にした育成は、定着率の向上にも直結するのです。
■ まとめ:育成の未来は、個人の内面にある
これからの人材育成に求められるのは、「教え込む力」ではなく、「引き出す力」です。内発的動機づけを高める育成は、本人の主体性・創造性を引き出し、組織の持続的な成長にもつながります。そしてなにより、それは「人が人らしく働ける環境」をつくることでもあります。
内側から燃える火は、外から与えられた灯よりも、はるかに強く、長く持続します。
企業がその火を絶やさず、じっくり育む姿勢を持つことこそ、これからの時代の“人が育つ組織”の条件と言えるでしょう。