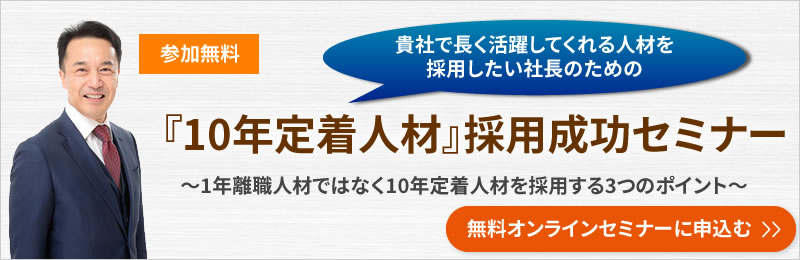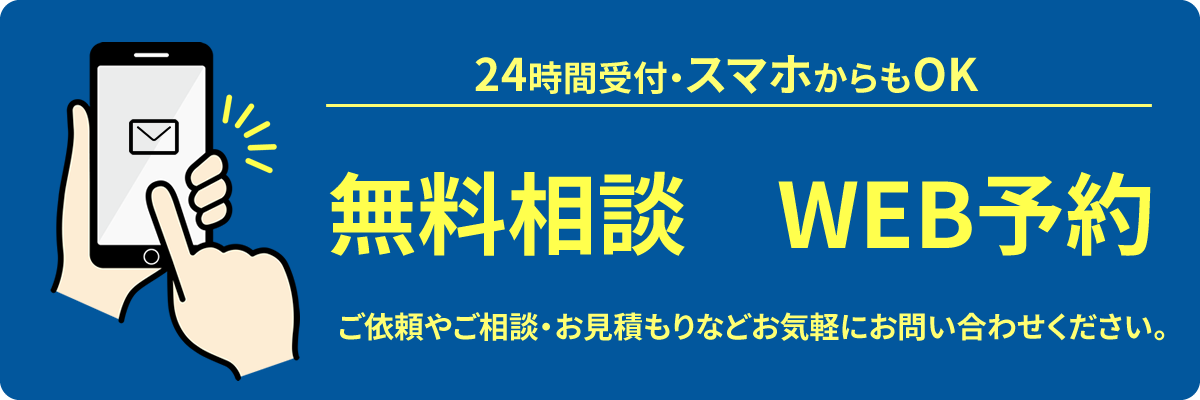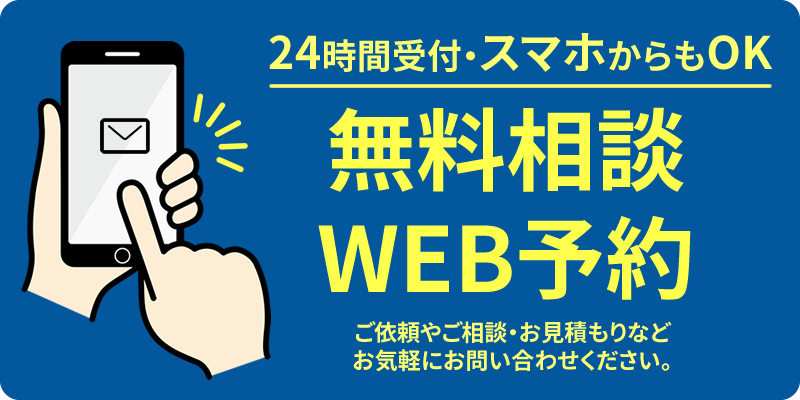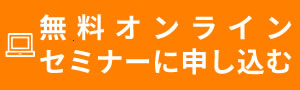心理的安全性が社員の定着率を向上させる理由と実践法
近年、ビジネスの現場でよく耳にするようになった「心理的安全性」という言葉。
Google社の調査によって注目を浴び、働く人たちのパフォーマンスやチーム力を高めるために重要な要素として広く知られるようになりました。
しかし、この「心理的安全性」が、社員の定着率に大きく影響することは、まだあまり知られていないかもしれません。
特に人材採用と定着に悩む中小企業にとって、この心理的安全性を意識するかどうかが、社員が長く働きたいと思う職場になるかどうかの分かれ道になります。
本コラムでは、「心理的安全性とは何か」「なぜ定着率に影響するのか」「どうすれば心理的安全性の高い職場をつくれるのか」についてお伝えします。
心理的安全性とは何か?
心理的安全性とは、「この職場では、自分らしく意見を言っても大丈夫」「失敗しても否定されない」と感じられる状態を指します。
具体的には、次のような状態です。
自分の意見やアイデアを発言しても否定されない
ミスをしても必要以上に責められない
自分の存在がチームに受け入れられていると感じられる
困ったときに誰かに相談できる
つまり、安心して自分を出せる環境が心理的安全性の高い職場なのです。
この心理的安全性が高いと社員は挑戦しやすくなり、意見交換も活発になり、チームの成果も高まることが多くの研究で明らかになっています。
なぜ心理的安全性が定着率に影響するのか?
採用活動に苦労している中小企業の多くが、「せっかく採用しても辞めてしまう」「特に若手社員が定着しない」といった悩みを抱えています。
この背景にあるのが、職場での心理的安全性の欠如です。
社員が職場を離れる理由は、必ずしも「給料が安い」「労働時間が長い」だけではありません。
実際、多くの離職理由には、次のような心理的な要因が隠れています。
・上司や同僚に否定された経験
・自分の意見が聞き入れられない環境
・失敗を恐れて発言できない風土
・ちょっとした相談ができない孤独感
これらが積み重なると、社員は「この会社では自分は受け入れられていない」「ここにいても自分らしく働けない」と感じ、やがて退職という選択肢を取るようになります。
特に中小企業では、人間関係が会社全体の雰囲気に直結しやすく、少人数だからこそ「心理的安全性の低さ」が社員一人ひとりに大きく影響します。
心理的安全性がもたらす3つの定着効果
心理的安全性が高い職場では、具体的に次のような効果が期待できます。
1. ミスや失敗を恐れず挑戦できる
「失敗したら怒られる」「責められる」という恐怖心がなくなることで、社員は安心して仕事に取り組むことができます。
挑戦する機会が増え、仕事へのやりがいを感じやすくなるため、結果的に定着につながります。
2. 人間関係のストレスが減る
職場のストレスの多くは、業務そのものよりも人間関係が原因と言われています。
心理的安全性が高い職場では、社員同士の信頼関係が生まれ、無駄なストレスが減ります。
3. 困ったときに相談できる
「困っているのに誰にも相談できない」「一人で抱え込んで苦しくなる」ことは、離職の大きな原因です。
心理的安全性の高い職場では、相談しやすい空気があるため、問題が起きても早期に解決できます。
中小企業が心理的安全性を高めるための3つの取り組み
では、具体的にどうすれば中小企業でも心理的安全性の高い職場をつくることができるのでしょうか。
今日から実践できる3つの取り組みを紹介します。
① 上司・経営者が「否定しない」姿勢を徹底する
部下や社員の意見を聞いたとき、「でも」「それは違う」などと否定していないでしょうか?
上司や経営者がまずは受け止め、共感する姿勢を持つことで、心理的安全性は一気に高まります。
② 小さな「承認」と「感謝」を積み重ねる
心理的安全性は、日々のコミュニケーションの積み重ねによって育まれます。
「ありがとう」「助かったよ」「その視点はいいね」といった小さな承認が、社員の安心感につながります。
③ 失敗事例をオープンに共有する文化をつくる
ミスや失敗を責めるのではなく、「失敗も学び」として全員で共有する文化をつくることで、「失敗しても大丈夫」という安心感が生まれます。
■まとめ
採用市場が厳しく、人材確保に悩む中小企業にとって、「採用活動」そのものも大切ですが、実は採用した社員が長く働きたいと思える環境づくりが、定着率を左右します。
そのための大きなカギが、心理的安全性です。
給料や労働条件を見直すことももちろん必要ですが、「ここにいていいんだ」「自分らしく働ける」と社員が感じられる職場であるかどうかが、長期的な人材定着の決め手になります。
今日から、職場で交わすひと言、部下への声かけ、ミーティングでの姿勢を見直してみてください。
小さな積み重ねが、辞めない会社・定着する会社への第一歩になります。