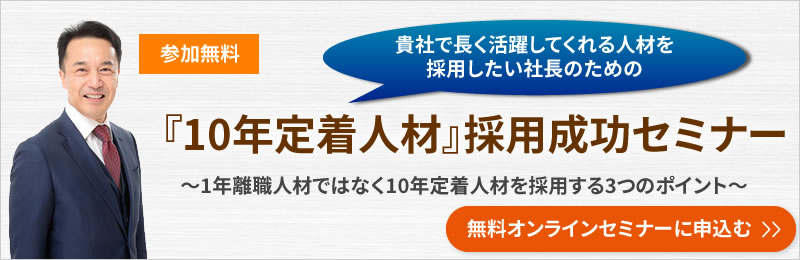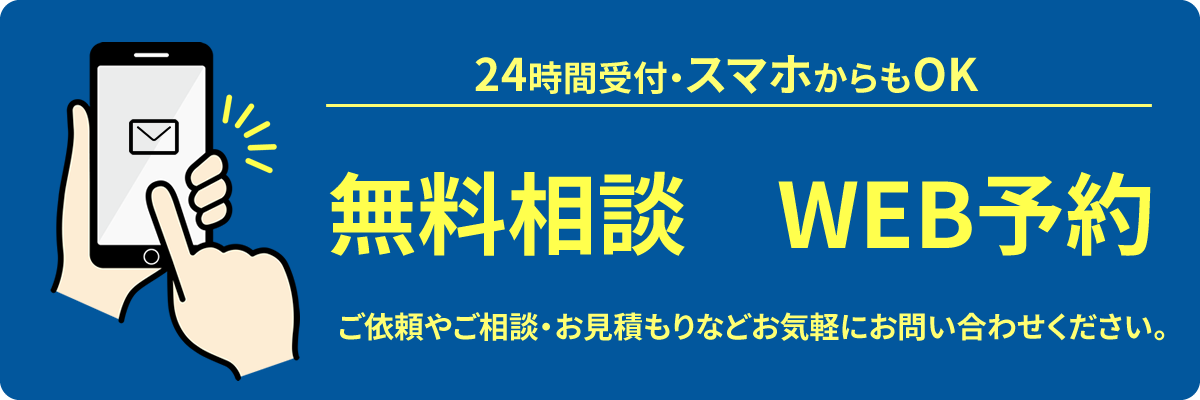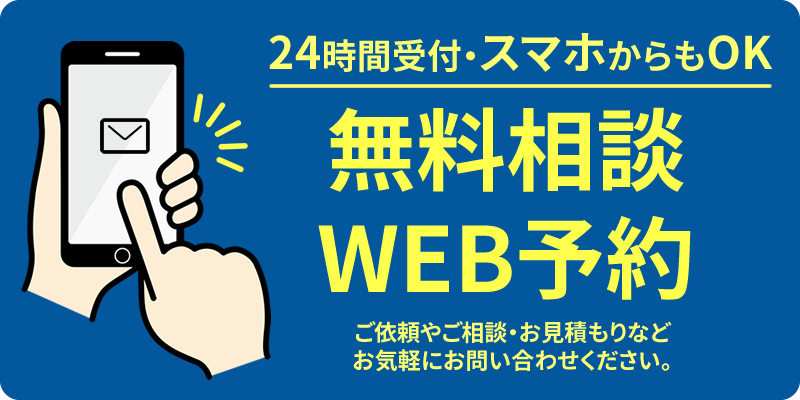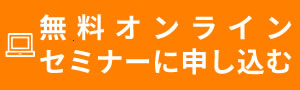新入社員がすぐ辞める理由とは?“共感設計”と“心理的安全性”で変わる定着率
「え?もう辞めたいの?」
人手不足に悩む企業が、ようやく努力の末に採用できた若手社員。
それなのに、入社からたった数週間で「すみません、辞めたいと思っています」と申し出が来る。そんな経験をされたことがある経営者や人事担当者も少なくないのではないでしょうか。
面接ではあれほど意欲に満ち、キラキラした目で「がんばります!」と語っていた若者が、なぜこんなにも早く気持ちを変えてしまうのか。企業側としては「最近の若者は我慢が足りない」「根性がない」と感じるかもしれません。
しかし、この“早期離職”には、実は共通する心理的・感情的なパターンが存在しています。
その本質は、「合わなかった」ではなく、「受け止めてもらえなかった」という感情の蓄積にあります。
■「辞めたい」の背景にある“静かな感情の変化”
本人が語る離職理由は多岐にわたります。
• 仕事内容が想像と違った
• 職場の雰囲気に馴染めなかった
• 上司が怖かった
• 話を聞いてくれる人がいなかった
こうした言葉の奥には、実は共通する“感情のすれ違い”が隠れています。
たとえば「仕事内容が違った」の裏には、「期待していたのに裏切られた」という失望。
「馴染めなかった」の奥には、「ひとりぼっちだった」「居場所がなかった」という孤独感。
そして「怖かった」「聞いてもらえなかった」という背景には、「わかってもらえない」という疎外感が存在しています。
人は、理屈ではなく“感情”で離職を決断します。
違和感や不安、寂しさが積み重なり、ある臨界点を越えたとき、はじめて「辞めたい」という言葉として表出するのです。
だからこそ、早期離職を防ぐには、「辞めたい」と言い出した瞬間ではなく、その前段階の“感情の変化”を捉える視点が不可欠です。ここに注目しなければ、いくら制度を整えても定着率の改善にはつながりません。
■ 入社直後の“感情のプロセス”に注目する
離職は、ある日突然決断されるものではありません。
そこには、日々の小さな“感情の積み重ね”があります。
以下は、ある若手社員の「辞めるまでの心の流れ」の一例です。
• 初日:緊張と期待を抱えて出社。早く馴染みたいと内心ワクワクしている
• 数日後:周囲からの声かけがなく、どこか疎外感を覚える
• 1週間後:質問しづらい空気を感じ、気を遣いすぎて萎縮
• 2週間後:「この環境で自分は成長できるのか」と漠然とした不安に襲われる
• 3週間後:出社が憂うつになり、徐々に「辞めたい」が芽生える
この一連の流れに共通しているのは、「感情が放置されている状態」です。
心に浮かんだ不安や疑問に対して、誰も反応を返してくれない。
誰にも打ち明けられず、相談もできず、孤立感が深まっていく。
これが、離職の“見えない前兆”なのです。
逆に言えば、ちょっとした声かけや共感、あるいは「その気持ち、わかるよ」という一言があるだけで、その心の流れは大きく変わります。
■ 早期離職を防ぐ“6つの具体策”
では、企業側として何ができるのでしょうか?
以下に、実践的な6つの対策を紹介します。
① 入社初日の「歓迎体験」を設計する
・ウェルカムレターや代表からの動画メッセージ、ランチ会を通じて“歓迎されている実感”を持たせる
② 1ヶ月間の1on1面談で不安の芽をつむ
・上司との週1面談に加え、メンターとの日常的な対話で「話せる場」を確保
③ 感情チェックツールや日報に「気持ち欄」を設ける
・週1回の簡易アンケートで“感情の変化”を見える化し、組織で共有する
④ 「意味」を語るマネジメントを徹底する
・「なぜこの仕事をするのか」「誰の役に立つのか」を明確に伝え、納得感と誇りを育てる
⑤ 成功体験を早期に設計する
・「ありがとう」と言われる経験、小さな達成感を意図的にデザインする
⑥ 職場メンバーとのつながりを意識的に作る
・雑談会、ランチ、オンライン交流など、横の関係性から“安心の土壌”をつくる
■ まとめ:辞めるのは“感情のスイッチ”が入るから
人は、論理ではなく感情で動きます。
だからこそ、就業規則や福利厚生を整備するだけでは不十分です。
大切なのは、“感情の設計”です。
「ここにいてもいい」と思えるか。
「わかってくれる人がいる」と感じられるか。
「この会社に貢献したい」と心が動くか。
それらは、制度ではなく“人の関わり”によって生まれます。
マニュアルより、声。
制度より、まなざし。
そこに本気の温度があるかどうかが、離職か定着かを分けるのです。