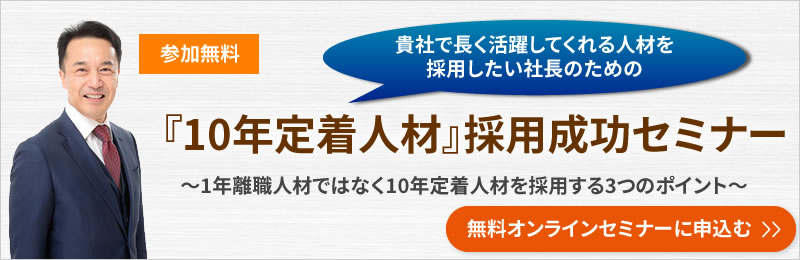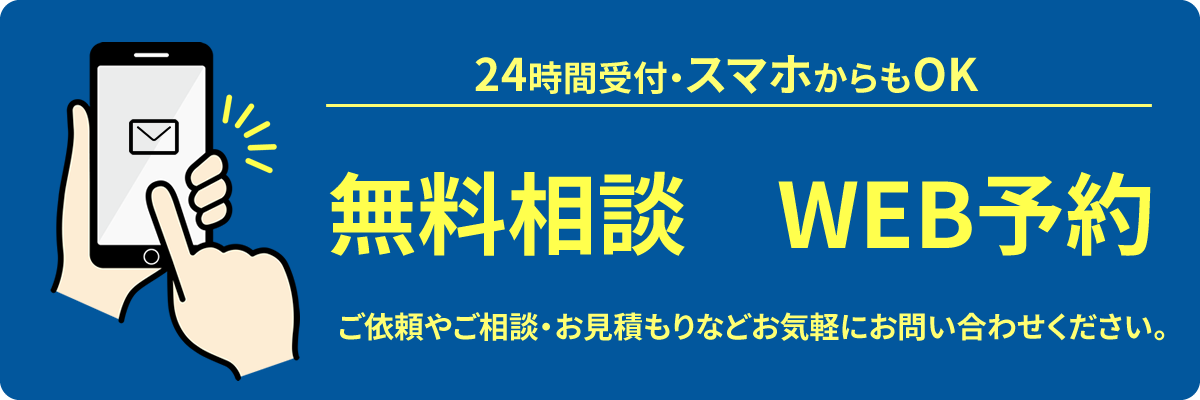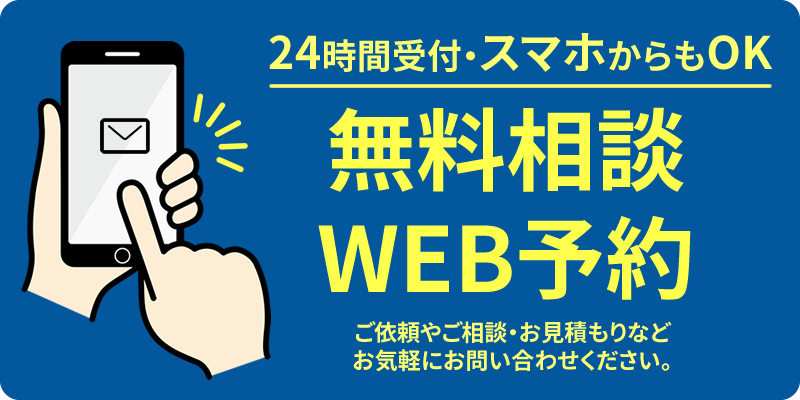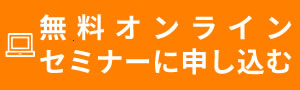最近の若者はすぐ辞める・・・その本当の理由は“感情”だった
「最近の若者はすぐ辞める」と嘆く経営者や上司の声を耳にすることがあります。
しかし、本当に「若者の根性が足りない」ことが原因なのでしょうか。
心理学的な視点からこの問いを深掘りしていくと、
新入社員が辞める職場と残る職場の「決定的な違い」が見えてきます。
「3ヶ月」という節目の意味
まず注目したいのは、「3ヶ月」というタイミングが持つ心理的な意味です。
新入社員にとって、入社直後の数週間は“新生活適応期”にあたります。
環境も人間関係もすべてが新しく、緊張と期待が入り混じるこの時期は、
心理学で言うところの「ハネムーン期」とも呼ばれています。
この期間は、職場に対してポジティブなイメージを持ちやすく、希望的観測が先行します。
しかし、3ヶ月目あたりから現実とのギャップが徐々に明確になってきます。
これは心理的には「現実接触のフェーズ」に入り、
組織文化、上司の態度、仕事内容、将来の展望などが
理想と現実として切り分けられていく時期なのです。
その結果、新入社員は「自分はこの職場に合うのか」「ここで働き続けられるのか」を
無意識のうちに判断しはじめます。
つまり、3ヶ月で辞める人が多いのは単なる気まぐれではなく、
脳と心が「この環境に適応できるかどうか」を見極める重要なタイミングなのです。
辞める職場に欠けている「心理的安全性」
では、新入社員が短期間で離職してしまう職場には、どのような要素が欠けているのでしょうか。
その最たるものが「心理的安全性」です。
これは、Googleが「成功するチーム」を研究する中で導き出した重要なキーワードで、
“自分の考えや感情を表現しても、否定されたり非難されたりしない環境”を意味します。
心理的安全性が低い職場では、新入社員は次のように感じる傾向があります。
・質問しづらい(無知と思われるのではないかと不安)
・自分の意見を言えない(否定されることへの恐れ)
・間違えることが怖い(責められる不安)
このような状況が続くと、やがて“感情的な孤立”が生まれてしまいます。
そして、その孤立感が強くなると「自分には居場所がない」「自分は必要とされていない」と感じ、
無力感とともに離職という選択に向かってしまうのです。
つまり、辞めていく新入社員の多くは「能力が足りない」のではなく、
「自分の居場所を感じられなかった」ことが原因なのです。
残る職場は「感情への配慮」がある
一方で、新入社員が定着する職場にはある共通点があります。
それは、感情への丁寧な配慮があるという点です。
たとえば、以下のような関わり方が日常の中に存在しています。
「最近どう?困っていることない?」と気持ちを尋ねてくれる上司
初めての失敗に対して「よく挑戦したね」と認めてくれる風土
「わからないことがあったら何でも聞いてね」と繰り返し伝える文化
これらはすべて、感情に寄り添う“共感的なコミュニケーション”であり、
組織の中に「感情を表現しても大丈夫な空気」が流れていることの証です。
特にZ世代と呼ばれる若手社員にとっては、
「自分の気持ちをわかってもらえるかどうか」が信頼関係の土台になります。
どれだけ待遇や制度が整っていても、そこが欠けていると「つながりがない」と感じてしまい、
早期離職の引き金になるのです。
新入社員が定着するためにできること
では、新入社員が長く働きたくなる職場にするために、具体的にどのような工夫ができるのでしょうか。
心理学的な視点から、3つのアプローチをご紹介します。
【1】感情に寄り添う問いかけを習慣にする
「仕事で困っていることはありませんか?」という質問を日常的に投げかけることで、
自分の感情を言語化する機会が増え、心理的な安心感が高まります。
【2】小さな承認を積み重ねる
「ありがとう」「よく頑張ったね」といった言葉は、
自己効力感を高め、「ここにいてもいい」と思える土台をつくります。
【3】感情を受容する仕組みを取り入れる
たとえば1on1ミーティングを定期的に開催するなど、
新入社員の感情や気持ちを受容する機会を設けることで
職場全体が“感情を大切にする文化”に変わっていきます。
まとめ:感情を大切にする職場こそ、定着する
新入社員が3ヶ月で辞めるかどうかは、
その人の甘えや根性の問題ではありません。
むしろ、職場がどれだけ感情を受け止め、共感し、安心をつくれるかが、
定着を左右する大きな要因となります。
感情を丁寧に扱える職場には、必ず人が根を張ります。
それこそが、本当の意味での「定着」であり、
人と組織がともに成長するための土壌となるのです。