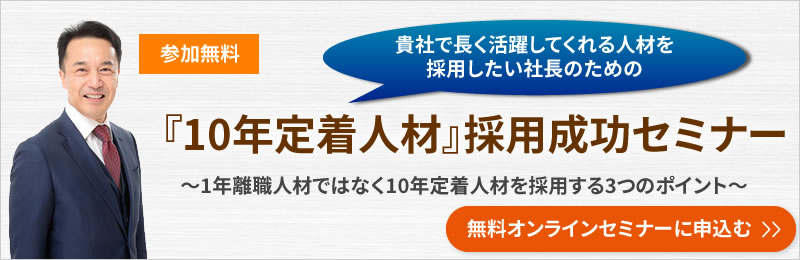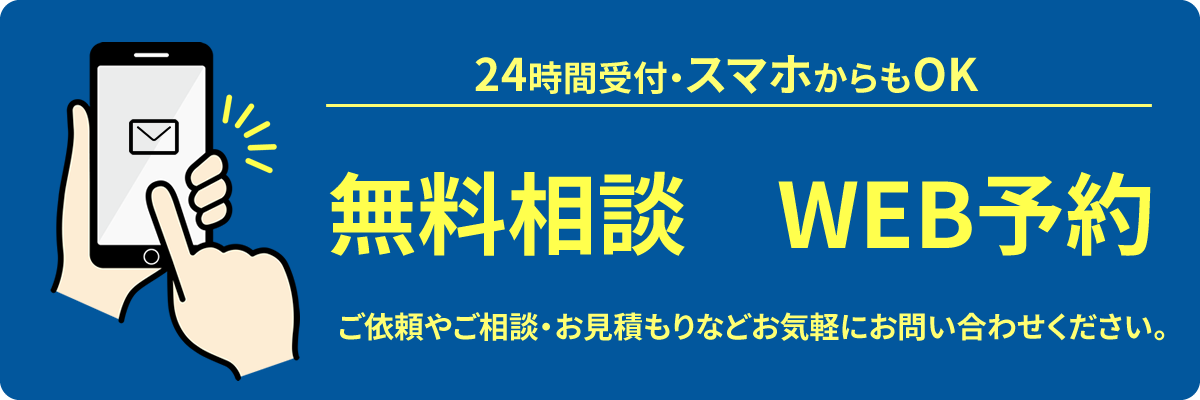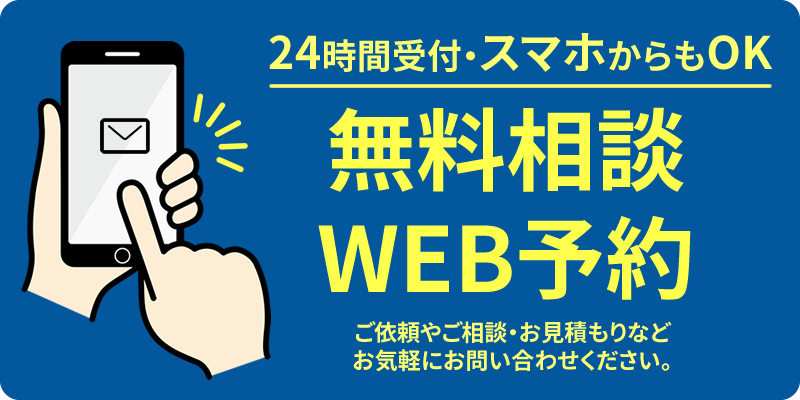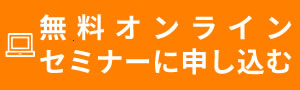若手社員の離職を防ぐ、見直したい3つの視点
「せっかく採用した若手社員が、1年以内に辞めてしまう…」 そんな悩みを抱える経営者や人事担当者の方も少なくないでしょう。
実際、厚生労働省の調査によれば、大卒社員の3年以内離職率は約3割。特に中小企業においては、採用や育成にかけた労力が水の泡となるばかりか、組織全体の士気や成長スピードにまで影響を及ぼしてしまうケースも少なくありません。
では、どうすれば「10年定着™」する人材を育て、辞めない職場を実現することができるのでしょうか?
本コラムでは、心理学と現場での定着支援経験をベースに、若手離職の“本質”と、長期定着を実現するための3つの視点をお届けします。
■若手社員が辞める「本当の理由」とは?
よく挙げられる退職理由には以下のようなものがあります。
・人間関係が合わなかった
・仕事の内容がイメージと違った
・やりがいが感じられなかった
これらは一見もっともらしく聞こえますが、実は表面的な理由に過ぎません。 実際には、次のような“感情の不一致”が背景にあることが多いのです。
・心理的安全性がなく、本音を言えない
・相談できない
・成長のイメージが持てず、将来が見えない
・会社や上司から大切にされている実感がない
心理学的に言えば、これらは「所属の欲求」や「承認欲求」が満たされていない状態です。マズローの欲求5段階説でも示されるように、人は生理的欲求・安全欲求の次に「所属したい」「認められたい」という欲求を持ちます。この2つの欲求が職場で満たされないまま時間が経つと、徐々に気力を失い、離職の選択をとってしまうのです。
■“10年定着™”につながる3つの視点
では、どうすれば若手社員が辞めない職場をつくれるのでしょうか? 重要なのは、「仕組み」よりも「関係性」と「感情」に注目することです。以下の3つが鍵になります。
① 心理的安全性のある職場づくり
「どんな意見を言っても否定されない」「わからないと言っても大丈夫」「失敗しても責められない」 そんな空気がある職場は、社員が“自分らしく”働くことができ、能力も最大限発揮しやすくなります。
特に日本の若手社員は「空気を読む」ことに長けている反面、「言いたいことが言えない」ストレスを抱えやすい傾向があります。だからこそ、上司や先輩が意識的に“安心できる空気”をつくることが定着の第一歩となります。
② 小さな成功体験を積ませる仕掛け
心理学では「自己効力感」という言葉があります。これは「自分にはできる」という感覚のことで、モチベーションと密接に関係しています。
この感覚を育てるには、“大きな成功”ではなく、“小さな成功”の積み重ねが有効です。 たとえば、「初めての電話対応をうまくできた」「先輩に褒められた」「資料を期限通りに提出できた」といった小さな達成経験を、上司や先輩が丁寧に言語化してフィードバックすることが重要です。
③ 上司が“信頼と期待”を言葉にする
若手社員の多くは、「自分は必要とされているか?」を非常に気にしています。 にもかかわらず、多くの職場では「できて当たり前」とされ、期待や信頼を伝える機会が失われがちです。
だからこそ、上司が日常の中で「期待してるよ」「頼りにしてるよ」と言葉にすることが、若手にとっての“安心”や“自信”につながります。
■よくあるNG対応と、そのリカバリー
最後に、定着支援の現場でよく見かける“NG対応”と、すぐにできる改善策をご紹介します。
× 「最近の若者は打たれ弱い」と決めつける
× 「自分で考えろ」とだけ言って放置する
× 「3年は続けてみろ」と根性論で押し切る
このような対応は、若手の心を閉ざし、関係性を悪化させてしまいます。
ではどうすればいいのか?
・定期的な1on1で“感情”や“考え”を言語化させる
・「最初の3ヶ月」に焦点を当てた伴走型の育成を行う
・成果よりも“姿勢”や“プロセス”に目を向けて承認する
これらの取り組みは、若手にとって「私はここにいていいんだ」という感覚を育て、結果的に長期定着につながります。
■まとめ:10年定着™は“関係性”から生まれる
若手社員の離職は、本人の根性や適性の問題ではありません。 職場の“空気”と“関わり方”が変われば、社員は辞めなくなります。
心理的安全性、自己効力感、そして言葉にされた信頼と期待。 この3つが整ったとき、若手社員は「ここにいたい」と思えるようになります。
10年定着™は夢ではなく、つくるもの。 その第一歩は、あなたの「関わり方」から始まります。