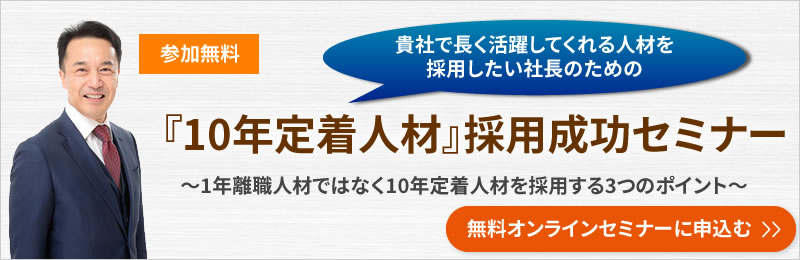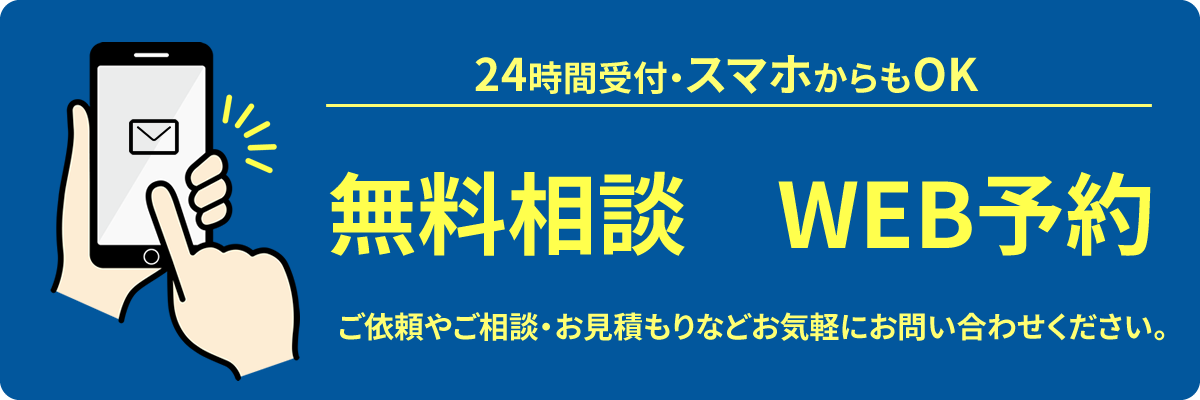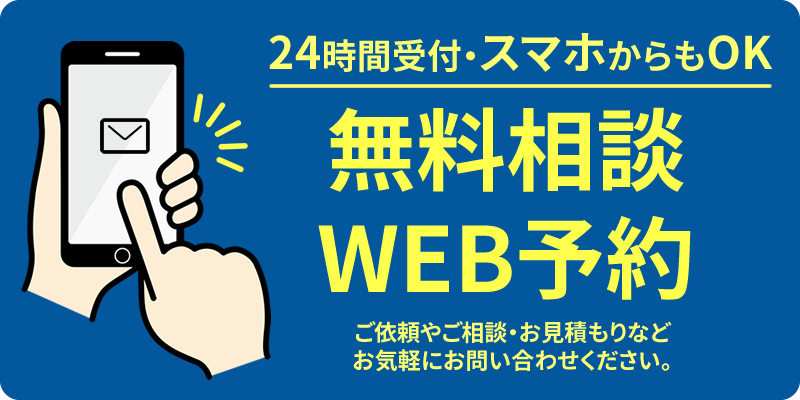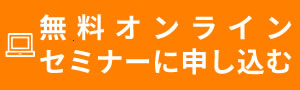部下が『辞めたい』と言い出す前に気づく、感情の小さな変化とは?
「まさか、あの子が辞めるなんて思わなかった……」
部下の突然の退職に驚き、言葉を失ったことがある──そんな経験を持つ経営者や管理職は少なくありません。
しかし本当に“突然”だったのでしょうか?
実は、「辞めたい」という決断に至るまでには、さまざまな小さな感情の揺れや違和感が、本人のなかで積み重なっています。そして、そのサインは本人の言葉にならない“行動”や“表情”、あるいは“沈黙”として、確かに周囲に現れているのです。
■ 感情は“静かに崩れていく”サインを出している
人は感情的なストレスや不満を抱えても、必ずしもそれを言語化して外に出すとは限りません。特に日本の職場文化では、「本音は言いづらい」「周囲に迷惑をかけたくない」という価値観が根強く、ネガティブな感情が“沈黙”や“無表情”という形で表出するケースが少なくありません。
また、人間の感情は“段階的に”崩れていきます。
例えば「納得できない指示を受けた」→「話を聞いてもらえないと感じた」→「この職場にいても評価されないのではないか」というように、小さな感情の波がやがて「辞めたい」という最終的な結論に変わっていくのです。
■ 見逃してはいけない「小さな変化」
では、具体的にどのような変化がサインとなるのでしょうか。以下は、実際の現場でもよく見られる「感情の変化の兆し」です。
• 発言のトーンや回数が減る
─ 以前は活発に発言していたのに、最近は会議中にほとんど話さなくなった。
• 笑顔や雑談が減る
─ 雑談を避けたり、表情がこわばっているように感じる。
• 小さなミスや遅刻・早退が増える
─ ミスの背景には集中力の低下や精神的な疲れがある可能性。
• 自己否定的な発言が目立つ
─ 「どうせ自分なんて」「やっても無駄だと思ってました」などの言葉が出てくる。
• 目を合わせない・報告が雑になる
─ 上司との心理的距離が広がっているサイン。
これらはどれも“爆発的”な変化ではありませんが、じわじわと職場へのエンゲージメントが下がっている証拠です。
■ 感情記憶と「辞めたくなる職場」の関係
人は“感情を伴う記憶”を強く保持するというのは心理学でよく知られた事実です。
この理論は「情動記憶」と呼ばれ、ポジティブな体験は職場への愛着ややりがいにつながり、ネガティブな体験はその職場から離れたいという気持ちを強化します。
例えば──
• 「自分の話をきちんと聴いてくれた」という体験は、信頼の記憶として残る。
• 「頑張っても認められなかった」という体験は、無力感や自己否定と結びつく。
つまり、日々の些細なやりとりが、「辞めたくなる職場」か「定着したくなる職場」かを決定づけているのです。
■ マネージャーができる“感情のケア”とは?
部下の感情の変化に早く気づくためには、上司自身が「感情に敏感な視点」を持つことが不可欠です。
以下に、感情ケアとして有効なアプローチをまとめます。
1. 小さな違和感を見逃さず、すぐ声をかける
違和感は時間が経つと“蓄積”されます。
「なんとなく元気がないな」と思ったら、気軽に「最近どう?」と声をかけること。
この“たった一言”が、本人にとっては「見てくれている」「気にかけてくれている」という安心につながります。
2. “評価者”ではなく“共感者”として話を聴く
心理学では“ラポール形成”が信頼構築の第一歩とされます。
つまり、「評価される」と感じると防衛反応が働き、「理解してくれる人」と感じたときに心が開かれるのです。
アドバイスや否定ではなく、まずは「そうだったんだね」と感情に共感する姿勢が重要です。
3. ポジティブな感情を意識的に伝える
社員の感情は、上司のちょっとした言葉で大きく左右されます。
「ありがとう」「助かったよ」「その工夫いいね」といった承認の言葉は、自己効力感を育み、モチベーションの安定につながります。
■ 「感情を見える化」する文化を育てる
個人の感情ケアだけでなく、組織として「感情を見える化する文化」を育てることも重要です。
• 毎週の1on1で“気持ちの変化”に耳を傾ける
• 朝礼や振り返りで感情を共有する機会を設ける
• 「最近、楽しかったこと・つらかったこと」を共有する場を作る
これらは、特別な制度を導入せずとも今日から実行可能なアクションです。
■ まとめ:感情の変化に寄り添う力が、定着力につながる
「辞めたい」と口にしたときには、すでにその決断は心の中で何度も反芻されてきたはずです。
だからこそ、その“前段階”にある小さな感情の変化に気づけるかどうかが、マネジメントの真価なのです。
部下の感情を無視せず、日々の小さな揺れに寄り添うこと。
それが、社員一人ひとりが「この会社で働き続けたい」と思える土壌をつくります。
感情は、見えないけれど、確実に“職場の空気”と“定着率”を左右しているのです。