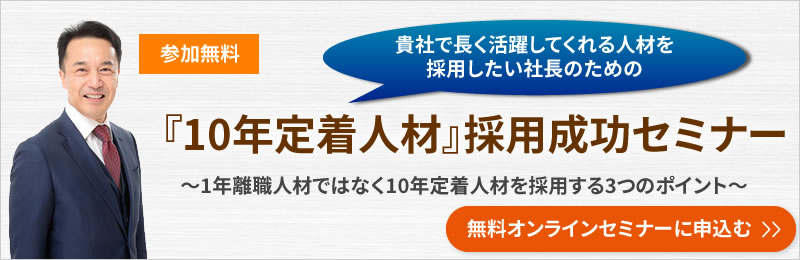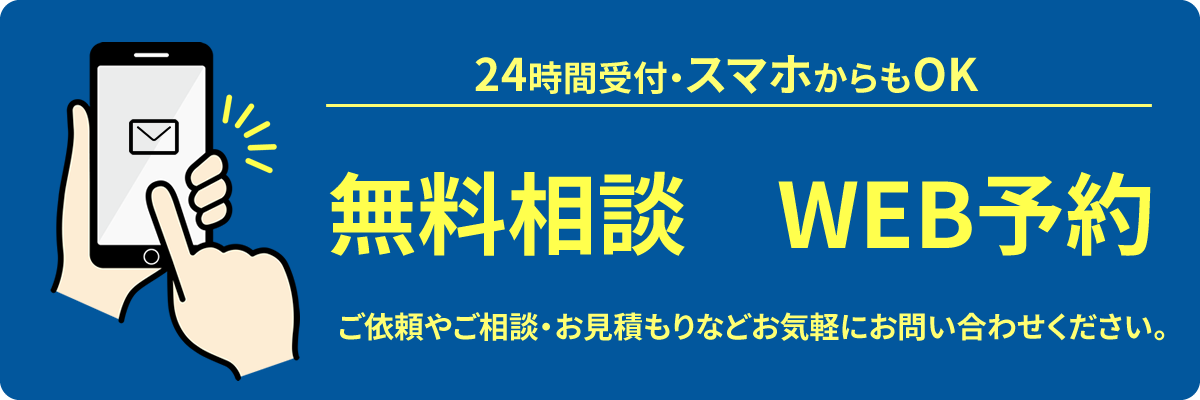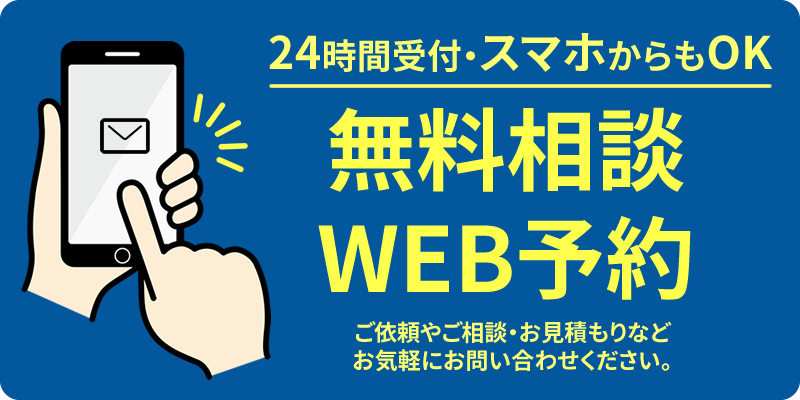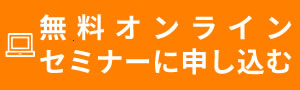部下が育たないのは、能力不足ではなく、任され不足
「最近の若手は育たない」「主体性がなく指示待ちだ」
多くの企業で聞かれる声です。しかし本当にそうでしょうか。実は“育たない”のではなく、“育てる環境が育っていない”可能性のほうが高いのです。とくに見落とされがちなのが、「任される経験」の欠如です。
人が最も成長するのは、知識を教わったときでも、研修を受けたときでもありません。
それは「責任ある仕事を任されたとき」です。
任されるという行為には、「責任」と同時に「信頼」がのせられます。
任された瞬間、人はこう変わります。
• 失敗しないように本気で考える
• 自分なりのやり方を探し始める
• 仕事を“自分ごと化”する
• 自ら動き、学び、調整をしようとする
つまり、人は“任された瞬間にスイッチが入る”のです。
逆に言えば、どれだけ教えても、任されなければ主体性は育ちません。
■ 任せているつもりが、実は「任せていない」
多くの管理職が「任せている」と言います。
しかし実態は次のどちらかです。
1. 細かく指示し続け、裁量を渡していない
2. 仕事だけ投げて、フォローも期待値共有もない=丸投げ
任せるとは「やらせること」ではありません。
それは 【役割】×【責任】×【裁量】×【伴走】 がそろって初めて成立します。
■ 任されない理由の多くは「部下の能力」ではなく「上司の不安」
任せられない管理職の本音はこうです。
• 「失敗されたら自分の責任になる」
• 「自分でやった方が早い」
• 「任せても結局やり直すことになる」
• 「教える時間がない」
つまり、部下の能力不足よりも、上司側の不安や経験不足がブレーキになっているのです。
しかし、この発想のままでは何十年経っても育ちません。
優秀な人材は、最初から優秀だったわけではなく、“任され経験”が多かっただけです。
■ 育つ任せ方:実践5ステップ
任せることで人を育てるには、上司側にも「任せる技術」が求められます。
以下は育成と成果を両立する任せ方のプロセスです。
✅ STEP0:任せる前提を整える(信頼の土台づくり)
任せるとは「評価」ではなく「期待」です。
日常的な声かけ、強みの言語化、存在承認など、土台がなければ任される側は“プレッシャー”にしか感じません。
✅ STEP1:タスクではなく「役割」で任せる
「この資料作っておいて」では人は育ちません。
「今回の会議準備の責任者を任せる」と言われて初めて、主体性が生まれます。
仕事を渡す=作業者になる
役割を渡す=当事者になる
✅ STEP2:目的・ゴール・期待値を明確に伝える
任せて失敗する最大原因は ゴールのズレ。
上司と部下の“成功イメージ”を一致させることが重要です。
• 目的(なぜやるのか)
• 成果イメージ(何をもって成功とするか)
• 優先順位・判断基準(迷ったときの軸)
✅ STEP3:やり方は任せるが、伴走は設計する
任せる=放置ではありません。
「手は離すが、目は離さない」が育成型マネジメントです。
• 進捗共有のタイミングを決める
• 上司はアドバイスではなく“問い”で支援
• 失敗しそうな箇所を先に共有しておく
✅ STEP4:結果ではなく“プロセス”を評価し、学習化する
部下が伸びるかどうかは「振り返りの質」で決まります。
• どんな工夫をしたか
• どこでつまずいたか
• 次に活かせる学びは何か
失敗を叱るのではなく 「経験を言語化し、自分の財産にする場」 をつくることが重要です。
✅ STEP5:成功を次の“任され機会”につなげる
「よく頑張った。次はこれを任せてみようか」
この連続が、キャリアと自信の土台をつくります。
■ 結論:育たないのではなく、育てていないだけ
任せない組織で人は育たない。
任されない人は主体性を持てない。
任され経験の少ない人は、自信を持てない。
そして
育つ人の共通点は「早くから任された経験がある」
育てる上司の共通点は「任せる勇気を持っている」
育てたいなら、教えるより先に任せること。
任せることが、最も強力で、最も効果的な育成投資です。
あなたの組織には、どれだけ「任されるチャンス」が存在していますか?